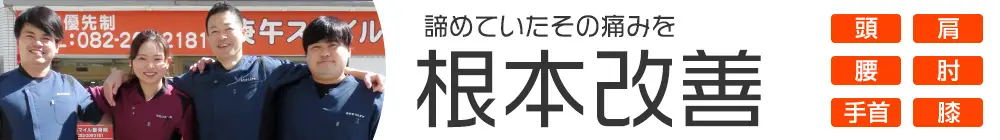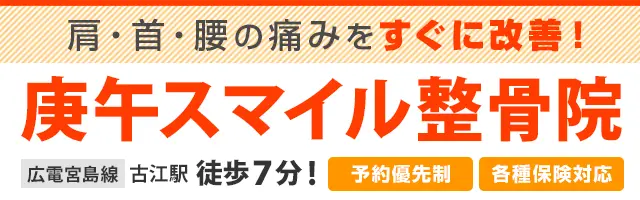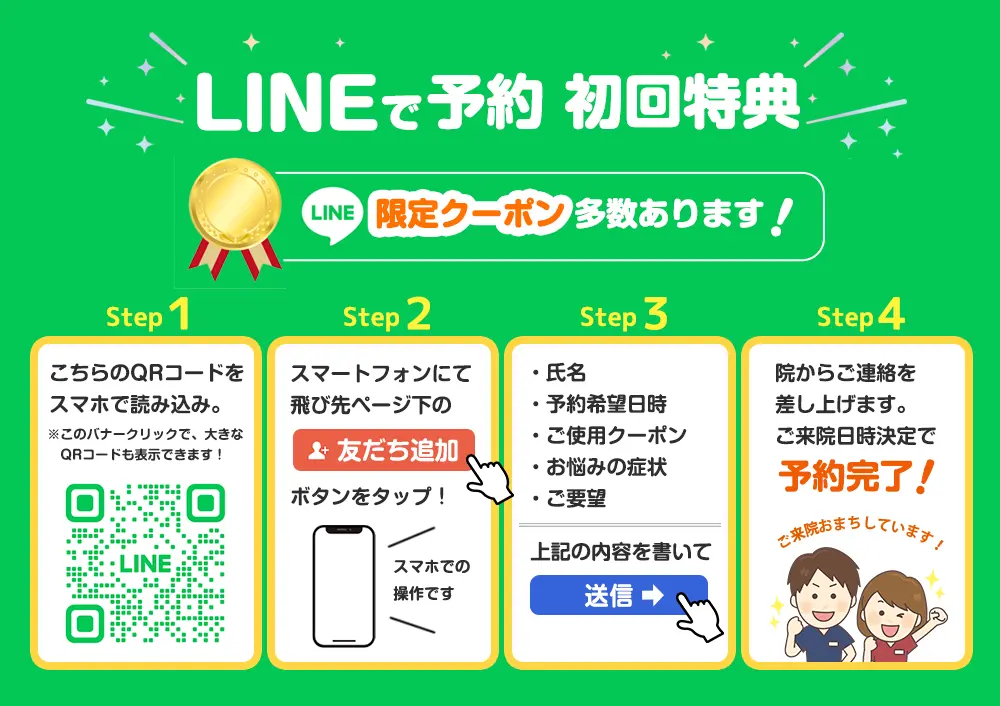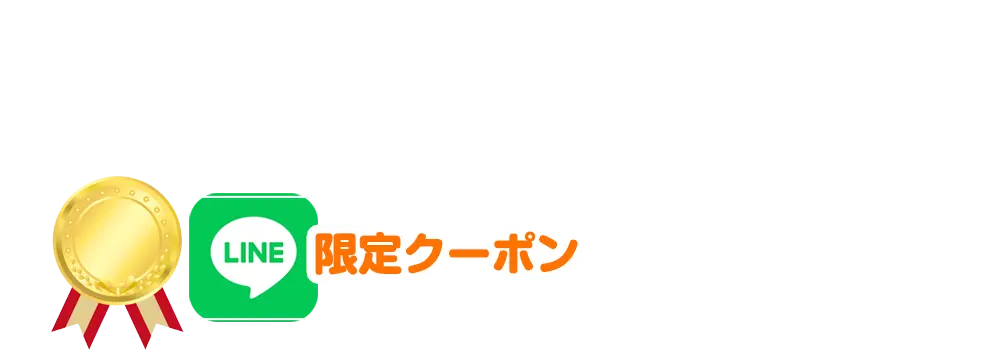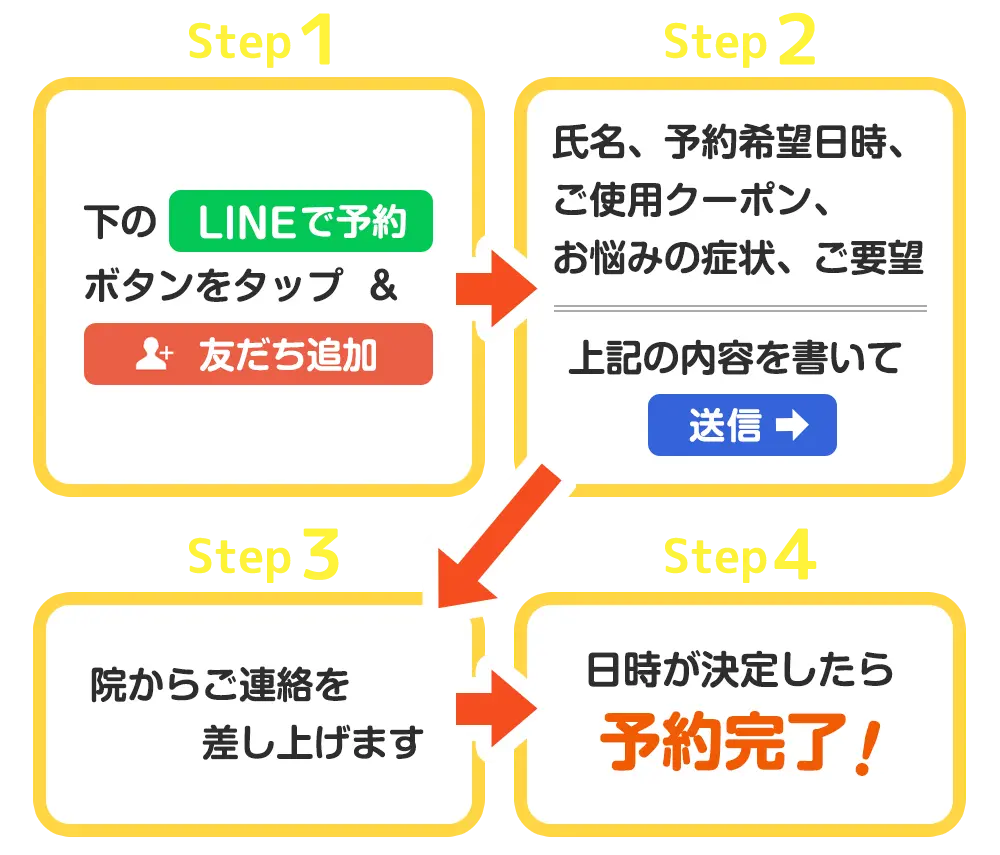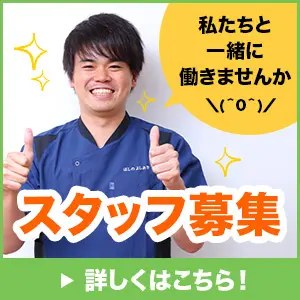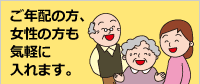肩甲骨はがし
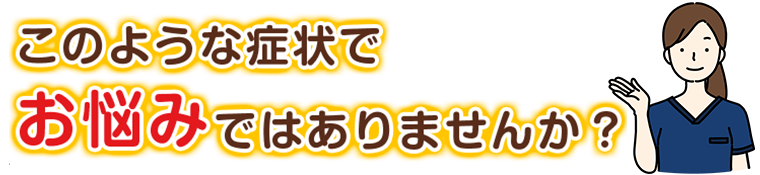
肩甲骨はがしに関する当院の考え
背中の上部に位置する逆三角形の平たい骨で、肩関節を構成する骨の一つです。胸を張ると自然に左右の肩甲骨が近付きますが、これが本来の正しい位置。しかしながら多くの人は姿勢の悪さや周囲の筋肉の影響で前側に肩が丸まっており、左右の肩甲骨が離れています。
肩甲骨は複数の筋肉に支えられていますが、なかには普段あまり使われない筋肉もあり(僧帽筋[そうぼうきん]、前鋸筋[ぜんきょきん]、肩甲挙筋[けんこうきょきん]など)、それらがこり固まると身体に不調が起こります。
肩の位置や動きなどの不調を改善させる施術が「肩甲骨はがし」です。
肩甲骨まわりの不調を放っておくとどうなるの?
肩甲骨のまわりには大小の筋肉、腱や靭帯、関節、血管が集まっています。それらがうまく機能しなくなると、肩こりや怠さなどの不調を誘発する可能性があります。
不調が起こるのは肩だけとは限りません。肩甲骨周辺から続く背中、腰、頭にも痛みや怠さが生じますし、さらには内臓の不調、慢性的な全身の疲れにもつながっていきます。
運動不足や長時間にわたるデスクワーク、ストレス、加齢などの影響で、肩甲骨が正しく動かない人が増えています。決して甘くは見られない状態です。
自分でできる改善方法
大切なことは「肩甲骨を本来の位置に戻し、肩の可動域を広げること」。固くなった筋肉をほぐすことで血行が促進され、痛みがやわらぎます。肩甲骨はがしのストレッチは壁やタオルなどを使って、ご自宅でも簡単に行うことができます。正しく行えばストレッチは大変効果的で、日常生活の中に習慣として取り入れることをおすすめします。自己流で始めるより最初だけ専門家に見てもらい、アドバイスをもらえると良いでしょう。当院でも効果の高いセルフストレッチをご指導させていただくことができます。お気軽にご相談ください。
同時に食生活の改善を行うと、より効果的です。ビタミンは体内の血流を促す、いわば潤滑油のような働きをします。体質改善を目的に積極的な摂取を心がけましょう。肩まわりに影響する栄養素にはビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12などがあります。
当院の肩甲骨はがし
「肩甲骨をはがす」と聞くと少し驚かれる患者様もいらっしゃいますが実際には肩甲骨の動きを滑らかにし、肩甲骨が本来持っている自由な動きを回復させることを目的としています。
当院の肩甲骨剥がしでは、肩甲骨とその周囲の筋肉・筋膜の癒着や緊張をほぐし、骨を「はがす」ようなイメージで動かしていきます。また同時に肩周りの筋肉のストレッチを行い、首、肩、肩甲骨にアプローチする庚午スマイル整骨院独自の特殊な手法です。
1.肩甲骨のモビリゼーション(可動運動)
肩甲骨を上下・左右・回旋などの方向に動かし、動きを引き出します。
2.筋膜リリース
肩甲骨の内側にある筋膜(特に肩甲下筋や菱形筋、前鋸筋)にアプローチし、癒着を解消します。
3.トリガーポイント療法
肩甲骨周辺の緊張した筋肉にピンポイントで圧をかけ、痛みや張りを軽減させます。
4.ストレッチ・運動療法
施術と並行して、広背筋・大円筋・小胸筋などのストレッチも取り入れ、可動域を広げます。
5.セルフケア指導
自宅でもできるセルフ肩甲骨剥がし(ストレッチや姿勢改善)を提案し、再発防止を目指します。
その施術を受けるとどう楽になるの?
肩甲骨はがしを行うと血流が促進され、それにより全身の免疫機能が向上し、感染症などへの抵抗力が高まります。筋肉量や柔軟性も上がるので、ふとした動きで体を痛めたり転んでケガをすることも減るでしょう。自然と背筋が伸び、胸まわりは上向きに。立ち姿や歩行姿勢も美しくなります。
もともとの正しい位置に肩甲骨が戻ると胸の開きが大きくなり、呼吸しやすくなります。猫背や巻き肩といった姿勢が同時に改善され、身体にまわる酸素量が増え、冷えやむくみの軽減も期待できます。
改善するための施術頻度は?
初期段階(症状が強い場合)
⚫︎頻度目安:週2〜4回(目安として1ヶ月〜3ヶ月程度)
⚫︎目的:短期集中的に可動域を広げ、筋肉の状態を改善
⚫︎補足:施術だけでなく、当院で指導させていただくセルフケアと併用すると効果が早まります
改善後〜メンテナンス
⚫︎頻度目安:月2〜4回
⚫︎目的:再発防止・身体の状態チェック
⚫︎補足:姿勢のクセや生活習慣を変えないと元に戻るため、当院で施術と伴わせて生活指導も行います。
整体・矯正・マッサージなど、当院における施術は
多岐に渡ります。ご気軽にご相談ください。
——————————————————————-★
庚午スマイル整骨院
——————————————————————-★
〒733-0822
広島県広島市西区庚午中4丁目19-28
TEL:082-208-2181
——————————————————————-★